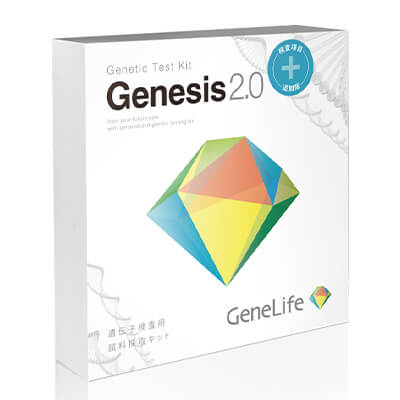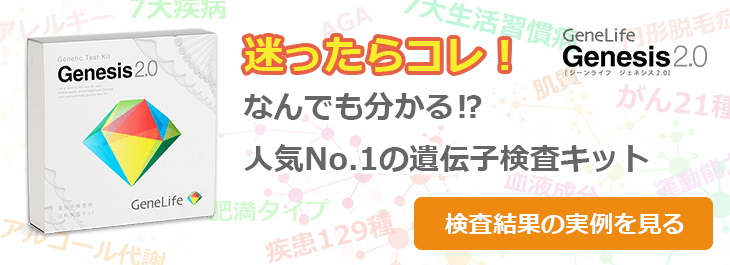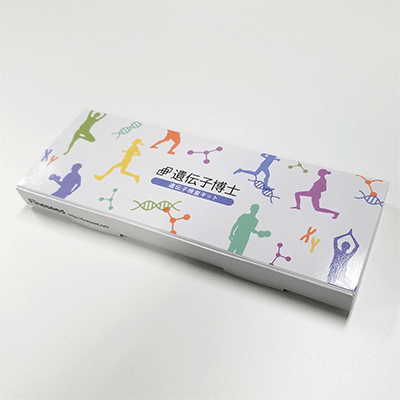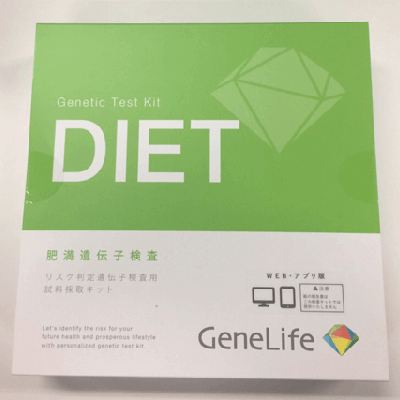ヒトの味覚は遺伝子の影響を受けます。生まれつき好きな味、苦手な味は、遺伝子によってある程度決まっているのです。
年齢とともに舌の性質が変わり、食べられなかったものが食べられるようになる、ということはあると思います。しかし遺伝子は基本的に変化しないもの。味覚は両親や先祖から受け継いだものなのです。
あなたがおいしい・まずいと感じる味覚、その判断は遺伝子によって左右されているのです!
もくじ
ヒトの味覚を決める遺伝子
味覚には、甘味(かんみ)、酸味、塩味(えんみ)、苦味、うま味という5つを基本味があります。それぞれの感じやすさは遺伝子によって決まっています。 人によっておいしい、まずいといった感覚が違うのは、遺伝子がひとそれぞれ違うからです。
うま味の感じやすさにかかわる遺伝子
うま味(旨味)は主にグルタミン酸やアスパラギン酸といったアミノ酸、グアニル酸といった物質から感じられる味覚です。
19世紀以前は科学的に立証されていなかった味覚で、欧米諸国では塩味、甘味の調和・バランスとしか考えられていませんでした。うま味に相当する表現が無かったため、日本語をそのまま読んだ「umami」が使われていたほどです。 2000年になってようやく、舌の感覚細胞にグルタミン酸を感じ取る受容体が発見されたことによって、うま味が認知されるようになったのです。
うま味にかかわるTAS1R3とTAS1R1
うま味の感じやすさは、TAS1R3とTAS1R1という遺伝子の影響を受けています。
TAS1R3遺伝子はアミノ酸と甘味の受容体に関する遺伝子です。天然糖であるスクロース、フルクトースや、人工甘味料であるサッカリン、アセスルファムカリウム、ダルシン、グアジノ酢酸といった物質を感じ取る能力に影響します。 この遺伝子の存在は、天然糖物質と人工甘味料が同じ味質をもたないメカニズムとして仮説されています。
TAS1R1遺伝子はアミノ酸やグルタミン酸の受容体に関する遺伝子です。 この遺伝子に関して、面白い逸話があります。現在は草食動物として知られるパンダは、もともと肉食動物でした。しかし約420万年前にTAS1R1遺伝子が変異し、肉のうま味を感じられなくなり、草食動物になったのではないかと考えられています。 元は肉食であった名残として、パンダは熊と同様のたんぱく質分解酵素を持っています。遺伝子が変化し味覚が変わるということは、食べるものも変わるという好例です。
苦味の感じやすさにかかわる遺伝子
苦味の感じやすさは、TAS2R38、TAS2R46、TAS2R19、TAS2R38といった遺伝子の影響を受けています。
ひとくちに「苦味」といっても、実は原因物質によって種類が違います。例えばコーヒーに含まれるカフェインを感じとりやすい体質でも、他の苦味を感じやすいとは限りません。
フェニルチオカルバミドの感じやすさ
フェニルチオカルバミド(Phenylthiocarbamide)という苦味物質は、TAS2R38という苦味受容体が関係しています。遺伝的にこの受容体を持たない人は、この物質が苦く感じます。 世界的には約7割の人がこの物質を苦いと感じますが、オーストラリア先住民のアボリジニでは58%程度、アメリカ先住民では98%が苦味を感じると言われています。
また、ヘビースモーカーはこの苦味にたいして鈍感である傾向があり、女性の方が男性よりも苦味を感じやすいと言われています。
カフェインの感じやすさ
主にコーヒーや紅茶に含まれるものとして知られるカフェイン(caffeine)の苦味は、TAS2R46遺伝子が関係しています。カフェインは緑茶、ウーロン茶、コーラや栄養ドリンクなどにも含まれており、遺伝子によって苦味を感じる程度が違います。 コーヒーを飲んで苦いと感じる人は、同じ量のカフェインが含まれたお茶を飲んでも、同じくらい苦味を感じるということです。
キニーネの感じやすさ
オランダ語のキニーネ(英名はキニン quinine)は、マラリアの特効薬として重宝された物質です。 特に1960年代に戦争の影響で暴騰しましたが、現在は人工的な抗マラリア薬が開発され、副作用のあるキニーネは用いられなくなりました。
強い苦味をもつ物質で、トニックウォーターの苦味剤として使われています。今でこそ清涼飲料水として知られるトニックウォーターですが、もともとはマラリア防止のための飲料で、医療用として多量のキニーネが使用されていました。 現在のトニックウォーターではキニーネの量は少なく、香料が代用されていることもあります。
キニーネの苦味にはTAS2R19遺伝子が関係しています。遺伝子型によっては、トニックウォーターが苦くない・あるいはとても苦いと感じるでしょう。
プロピルチオウラシルの感じやすさ
TAS2R38遺伝子は、プロピルチオウラシルという物質の苦味に関係しています。 プロピルチオウラシルは、甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)という甲状腺ホルモン分泌量が過剰になる疾患の治療に用いられる物質です。さまざまな副作用と起こす物質でもあり、現在は抗甲状腺治療の第一選択薬として推奨されていません。
プロピルチオウラシルはキャベツやブロッコリーにも含まれており、TAS2R38の遺伝子型によっては苦味を感じやすい人もいます。キャベツが嫌いな人は、TAS2R38変異型のせいかも?
味覚がわかる遺伝子検査キット
味覚に関する遺伝子の研究は、まだまだ発展途上分野です。遺伝子検査キットでわかる味覚は、人間がもつ味覚の一部です。 いつかもっと遺伝子の研究が発展すれば、ひとそれぞれの味覚にあった料理が提供される、という時代がくるでしょう。
遺伝子検査もまだまだ浸透していない分野です。「遺伝子検査をしたことがある」というだけでも話題性抜群! うま味を感じやすい遺伝子をもつ人は、「味がわかる」とグルメ自慢してみてもいいでしょう。おいしいお店に説得力が出るかもしれません。カフェインの苦味を感じにくい人は、コーヒーや紅茶が好きな理由として語ってみるのも面白いですね。