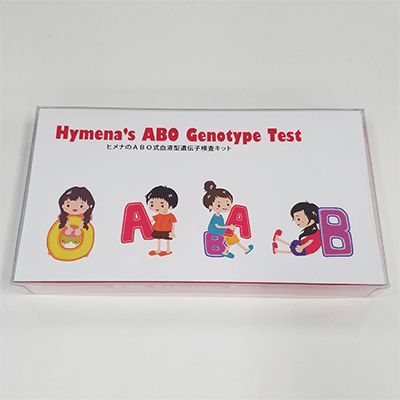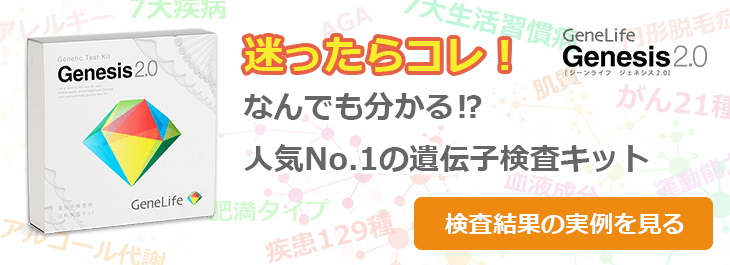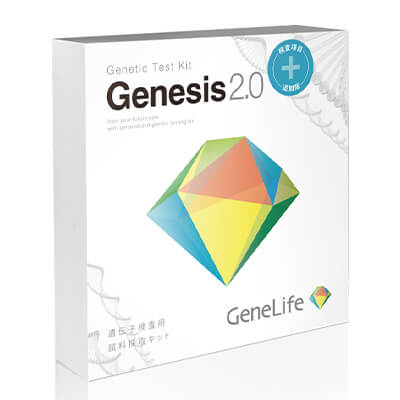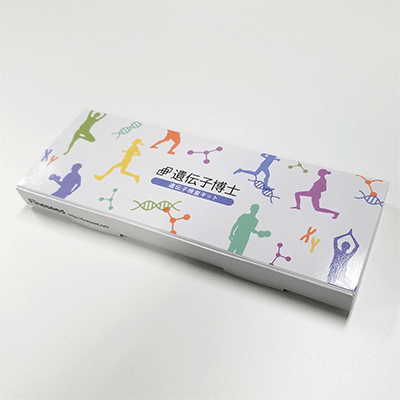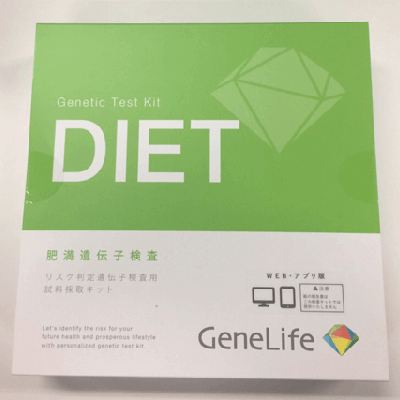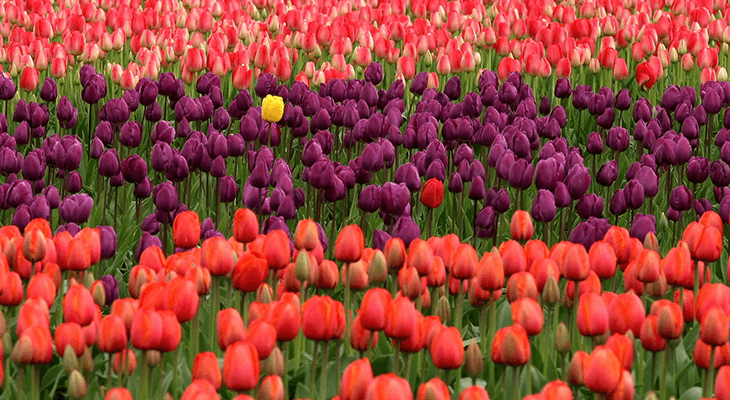
血液型といえば、A型、B型、O型、AB型といったABO式血液型が一般的です。しかしABOというくくりでは定義できない、非常に珍しい「稀血(まれけつ)」という血液型も存在しています。
稀血(まれけつ)とは?
稀血(まれけつ)とは、献血や血液検査等での出現頻度が1%以下と非常に珍しく、輸血を行う際にその確保が困難となる可能性のある血液型のことを言います。ABO式やRh式などの血液型分類の定義に当てはまらないことから、「まれな血液型」とも呼ばれています。
稀血の種類
稀血はそれぞれの血液型分類において存在しています。稀血の中でも検出頻度が100人に1人から数千人に1人の割合までをII群、II群より検出頻度が低いものはI群として分類されています。
ABO式血液型における稀血
ABO式血液型は、1900年にオーストリアのラントシュタイナーが発見した血液の分類方法のこと。人の血清に他の人の赤血球を混合すると凝集する(固まる)場合と凝集しない場合があることから血液に型があることが発見したものです。
| 稀血の種類 | 検出頻度 | 稀血における分類 |
|---|---|---|
| ボンベイ型 | 30万人に1人 | I群 |
| パラボンベイ型 | 30万人に1人 | I群 |
ボンベイ(Oh)型
Bombay(Oh)は、赤血球からA抗原、B抗原が検出されないため、通常の血液型検査ではO型と判定されてしまいます。しかし普通のO型が持たない抗H抗体を持っており、O型を含むH抗原をもつ血液を輸血できません。
ボンベイ型は100万人に一人という希少な血液型で、日本では数十人しか確認されていません。特にOh(ボンベイ型のO型)は輸血可能な血液が少なく、有事に備えて自身の血液を血液バンクに冷凍保存しておくことも考える必要性があります。
para-Bombay(パラボンベイ)型
para-Bombay(パラボンベイ)型はボンベイ型の派生型全くH抗原が検出されないボンベイ型とは違い、唾液からH抗原の検出可能です。そのため、A抗原とB抗原が弱い反応を見せることがあります。ただし、輸血に関してはボンベイ型と同じでO型を含むH抗原をもつ血液を輸血できません。
Rh式血液型における稀血
Rh式血液型は、1937年にオーストリアの医学者カール・ラントシュタイナーとアレクサンダー・ヴィナーがD抗原を発見したのがはじまり。実験で使用したアカゲザル(Rhesus Monkey)の頭文字が名前の由来となっています。
| 稀血の種類 | 検出頻度 | 稀血における分類 |
|---|---|---|
| -D-(バーディーバー)型 | 20万人に1人 | I群 |
| Rh null(Rh ヌル, ―――, バーバーバー)型 | 300万人に1人 | I群 |
| Rh mod(Rh モッド)型 | ― | I群 |
-D-(バーディーバー)型
-D-(バーディーバー)型はRh血液型における稀血の1つで、通常Rh血液型を構成するC・D・Eの抗原のうちCとEが存在しない血液型のこと。通常の検査では、D抗原の有無でRhの陽性と陰性を判断するので、見た目上Rh+(陽性)として扱われてしまう可能性があります。
日本人の20万人に1人いるといわれていますが、実際に検出される頻度はさらに低いといわれています。輸血を行う場合はCとEの抗原が無いことで抗体(抗Rh17)を生み出してしまう可能性から、同じ-D-(バーディーバー)型の血液を輸血しなければなりません。
Rh null(Rh ヌル, ―――, バーバーバー)型
Rh null型は、血液中に全てのRh抗原がしない血液型のことを言います。1万人に1人で存在するとされており、実際に世界中で43人しか確認されていません。あまりの希少さに専門家から黄金の血とも呼ばれています。
輸血について了承し、各国の検査機関に登録を行っているのは、ブラジル・日本・中国・アメリカ・アイルランドに住むたった6名しかいないとのこと。
Rh mod(Rh モッド)型
Rh mod(Rh モッド)型は、Rh null型がRh抗原を全く持っていないのに対し、極めて弱いRh抗原の反応がある血液型のことを言います。反応が弱いため、検査においてRh null型と誤認される可能性があります。
その他血液型分類における稀血
稀血には他にも以下のような血液型があります。ABO式とはずいぶんかけ離れた表記になっていますが、血液型の判定方法はABO式だけではありません。MNSs式、P式、ルセラン式などといった血液型分類の仕方があります。
| 稀血の種類 | 検出頻度 | 稀血における分類 |
|---|---|---|
| p(スモールピー)型 | ― | I群 |
| Ko(ケーゼロ)型 | ― | I群 |
| Fy(a-b+)型 | 100人に1人 | II群 |
| Fy(a-b-)型 | 0人(未発見) | I群 |
| Di(a+b-)型 | 500人に1人 | II群 |
| I(-)型 | ― | I群 |
| Kx(-)型 | ― | I群 |
| En(a-)型 | ― | I群 |
| Lan(-)型 | ― | I群 |
| Ok(a-)型 | ― | I群 |
稀血ではないが珍しい血液型
稀血ほど出現頻度は少なくないのですが、稀血に分類するには少し多く存在する血液型もあります。
Rh-型
その他珍しい血液型で最もポピュラーなのは、このRh-(アールエイチ・マイナス)型でしょう。日本人の99.5%はRh+型といわれ、Rh-型の人は200人に1人という珍しいタイプです。 Rh型はD抗原の有無によって判別され、D抗原陽性は+、D抗原陰性は-で表現されます。A型のRh+といった分け方になります。
Rh-型は珍しい血液型のタイプではありますが、稀血の中では数が多く、もし輸血が必要になった際にも「血液が無い」なんてことにはなりません。
シスAB型
AB型の亜型となる珍しい血液型がシスAB型と呼ばれるもの。通常A型遺伝子とB型遺伝子の組み合わせによってAB型と判断されるのです。しかし、これがシスAB型の場合は血液中に突然変異によるAB型遺伝子というものが現れ、O型遺伝子と組み合わさることによって、AB型であるにもかかわらずO型と診断を受けることがあります。
同じ血液型はいない?
血液型は、赤血球、血小板、白血球、血漿などに存在する数百種類の抗原の組み合わせを規則性に従って表現したものです。実際の血液型は数兆通りあるという説もあり、厳密には世界で自分と同じ血液型の人は存在しないともいわれています。
しかし輸血という点でいえば、厳密な血液型が違っても血液の凝集(固まること)がなければ問題はありません。稀血の人は血液バンクに自身の血液を保管しておいたほうがいいかもしれませんが、一般的には多少の違いでは輸血に影響することはないのです。