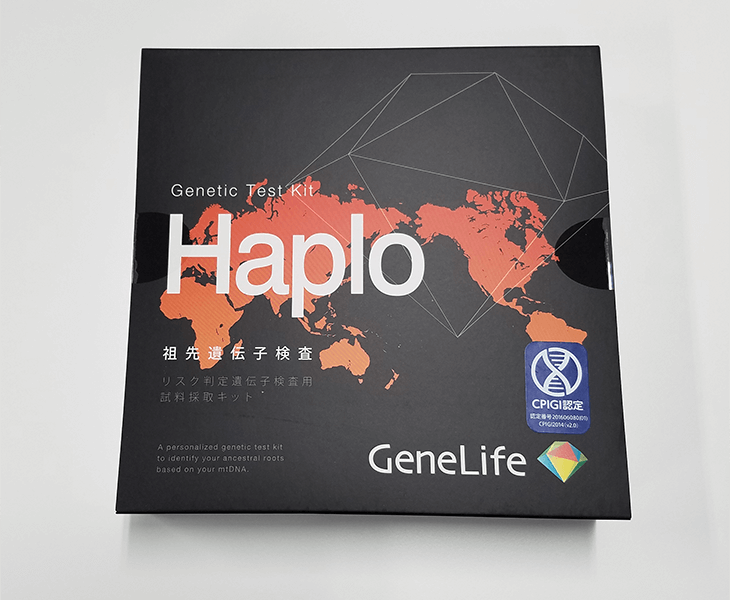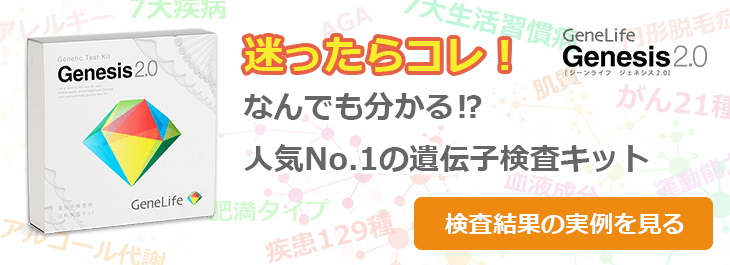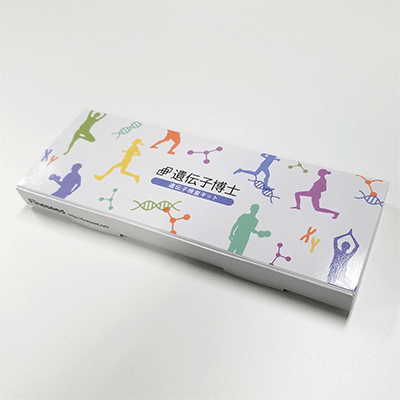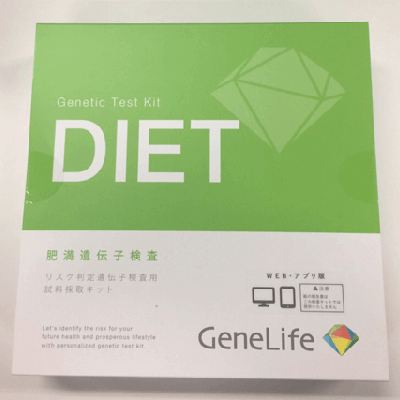8月13日から16日はお盆の期間です。 日本では祖先の霊をお迎えし、共に過ごす期間とされています。
海外でも、日本と同様に祖先の霊を祭る日があります。 世界のユニークなお盆祭りをご紹介します。
もくじ
世界のお盆祭り
キリストの復活祭「イースター」

キリスト教
「イースター(Easter)」は「復活祭」とも呼ばれ、キリスト教で最も重要とされています。
十字架にかけられて死んだイエス・キリストが、三日目に復活したことを記念するお祭りです。
西方教会(カトリックやプロテスタント)では、イースターは「春分の後に来る、最初の満月の後の日曜日」と定められています。
これはイエスが十字架にかけられたのが金曜日で、三日目にあたる日曜日に復活したことにちなんでいます。
名前の由来は春の女神「エオストレ」?
イースターと呼ばれる由来は、実は判明していません。
一番有力とされているのは、英国人の祖先アングロ・サクソン人が信じていた春の女神「Eostre(エオストレ)」からきたと言われる説です。
もともとキリスト教のお祭りではなく、春の訪れをお祝いしていたお祭りともいわれています。
カラフルな卵「イースターエッグ」
カラフルに染めた卵「イースターエッグ」は生命の始まりを意味し、キリストの復活を象徴しています。
ゆで卵であったり、プラスチックの模型、卵形のチョコレートを使ったりします。
「エッグハント(卵狩り)」や「エッグロール(卵転がし)」といった遊びもあります。
ウサギが隠したというイースターエッグを探す「エッグハント」は、中におもちゃやお菓子が隠されていることから子どもたちに人気のイベント。
殻を割ってしまわないように転がす「エッグロール」は、毎年ホワイトハウスでも行われます。 長い柄のスプーンを使い、芝の上でイースターエッグを転がすレースゲームです。
ウサギは繁栄を意味する
イースターエッグと並んでお祭りのシンボルとなっている「ウサギ」。
ウサギは繁殖力が強いことから、「繁栄と多産」のシンボルとして「イースターバニー」と呼ばれています。
キリストの苦難を想う「セマナサンタ」

キリスト教
こちらもキリスト教のお祭り。イースター前の1週間で「聖週間」とされます。 3月末~4月下旬ごろに行われ、キリストの復活に至るまでの受難や死に想いを寄せる日です。
お墓を掃除する日「清明節(せいめいせつ)」
中国
1年は24節気に分かれており、春分から15日目(第5の節気)が清明です。
中華系の人々は、先祖の墓に線香をあげてお参りします。 清明節は「民族掃墓節」(民族全体でお墓を清掃する日)と定められています。
日本のお盆の由来「鬼節(おにぶし)」
中国
こちらも中国のお祭り。鬼節(quijie)。
閻魔(えんま)大王が冥界の門を開け、冥土の鬼の魂がこの世に出てくるとされています。 日本の中元やお盆の由来と言われる行事です。
鬼節の「鬼」は必ずしも悪い鬼を指すものではありません。 しかし、死者の霊があふれる日であることから、鬼節にはいくつかのタブーがあります。
- 水辺で遊んではいけない(水難事故で死んだ霊に足を引っ張られる)
- 夜間に洗濯物を干さない
- 人の気配がしても振り向かない
- 壁に寄り掛からない
- お金を拾ってはいけない
- 徹夜をしない
鬼節の期間に中国を訪れることがあればご注意を!
日本のお盆「盂蘭盆会(うらぼんえ)」

仏教
「盂蘭盆会(うらぼんえ)」は、いわゆる日本の「お盆」。 サンスクリット語の「ウラバンナ」(またはウランバナ)が由来で、「逆さ吊り」を意味します。
死後、地獄に落ちた人々は逆さ吊りの刑を受けると考えられていました。 お盆の由来として、以下のようなエピソードがあります。
目連尊者と地獄の母
お釈迦様の弟子である「目連尊者(もくれんそんじゃ)」は、強い神通力(超能力)を持っていました。
神通力を使い、亡くなった母の姿を見ると、地獄の餓鬼道(飢えと渇きの地獄)に落ちて苦しんでいる様子が見えました。
目連尊者がお釈迦様に母を救う方法を尋ねたところ、僧の修行が一区切りとなる7月15日(旧暦)に供物を用意して功徳を積みなさいと言われました。
たくさんの供物を用意し祈り続けたところ、無事に母は成仏できたのです。
母だけでなく他の人々も救いたいと思った目連尊者は、毎年7月15日に供養をするようになりました。
日本のお盆
明治時代、江戸時代から使っていた旧暦から西洋の新暦が採用され、新旧の暦に1か月のずれが生じました。
京都の「五山送り火(ござんのおくりび)」や長崎の「精霊流し(しょうろうながし)」などもお盆の行事です。
なすやキュウリのお供え物「精霊馬」
なすやキュウリに割りばしや爪楊枝を刺し、動物のような形でお供えする「精霊馬(しょうりょうま)」は、祖先の霊が乗るためのものです。
キュウリの馬は早く霊をお迎えするためのもので、なすの牛は現世からたくさんのお供え物を積んで帰れるように、という意味があります。
タイの灯篭流し「ローイ・クラトン祭」

タイ
農民の収穫に恩恵の深い水の精霊に感謝をささげ、罪や汚れを水に流し、魂を清めるお祭りです。 旧暦12月の満月の夜(新暦11月頃)に行われます。
川に灯篭(とうろう)を流すことから、ロイ(流す)クラトン(灯篭)と呼ばれます。
日本でもお盆に灯篭流しをするので、共通のルーツを感じますね。
街中ガイコツだらけ!「死者の日」

メキシコ(ラテンアメリカ諸国)
お墓を骸骨人形や蝋燭などで派手に装飾し、お酒を飲んで楽しみながら死者を弔う日です。 カトリックにおける諸聖人の日である11月1日と翌2日に行います。
1日は子どもの魂、2日は大人の魂が戻る日とされています。 それにあわせてお供え物がお菓子からお酒に変わります。
市街地はマリーゴールド(死者の花と言われる)の香りに包まれ、露店が立ち並びます。 人々は骸骨をモチーフにしたフェイスペイントやマスクをかぶるなど、死者の仮装をして出歩きます。
明るく楽しく祝うのが特徴で、死を恐怖するのではなく、あざ笑うのが流儀です。 メキシコでは、死は恐れるものではなく、生があればいずれ死が訪れると考えられ、死を「生の象徴」と捉えられています。
生贄の祭り「イード・アル=アドハー」と「イド・アル=フィトル」
イスラム教
ラマダーン明けの祝祭です。「犠牲祭」という意味があります。
正装してモスクに集い、牛、羊、山羊(やぎ)などの家畜を生贄(いけにえ)に捧げます。
生贄にする家畜には条件があり、ある程度の年齢に達しており、失明や病気、足の障害が無いものでなくていけません。
また、生贄にされた肉を売ることはできず、3等分にします。 3分の1を食べ、3分の1をプレゼントし、残りは貧しい人に分け与えます。
お盆の無い国
オランダ、フランス、ミャンマーなどの国々では、お盆のような行事がありません。
フランスでは決まった時期にお墓参りするという習慣が無く、人それぞれなんだとか。 お墓に供えるのは「菊」が主流です。
ミャンマーは仏教国ですが、一族のお墓というものがありません。お墓を訪れて代々継ぐという考え方が無く、個人個人にお墓があります。
まとめ
お盆のルーツとも思える似たお祭りもあれば、陽気に歌い騒ぐものもあり、世界にはさまざまなお盆祭りがありますね。
日本人の祖先は、その多くが中国大陸から来たと考えられています。 中には東南アジアから海を渡り、北から極寒の地を越えてやってきた人々もいました。
ひょっとするとあなたのご先祖様は、お盆とは全く違う祭られ方をしていたのかもしれません。
祖先のルーツがわかる遺伝子検査キット
日本人の祖先は、遺伝子のタイプによっていくつかのグループに分けられています。
ハプログループによって日本へ来た経路が異なり、ルーツとなる地域も違います。
祖先のルーツを知り、はるか昔のご先祖様を日本のお盆とは違うスタイルで祭るのもいいですね。
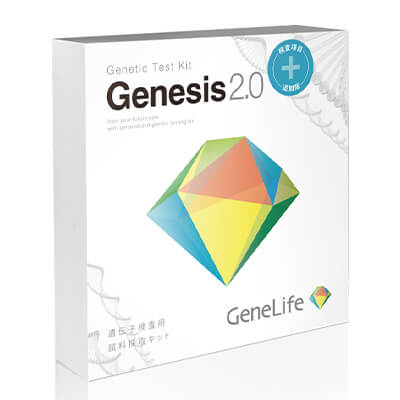
GeneLife Genesis 2.0 Plus(ジーンライフ ジェネシス プラス)
かかりやすい病気、太る要因、肌質、祖先のルーツ、お酒の強さなど、さまざまな病気・体質に関する項目を一度に検査できるキットです。 総合価格¥14,900